Things that I used to do.
役に立たない事ばかり
2025年4 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
最近の記事
カテゴリー
- 1.始めるにあたって (1)
- airplane (13)
- AUDIO (129)
- automobile (89)
- bicycle (13)
- books (21)
- boots (7)
- clothing (9)
- crafts (44)
- DESIGN (53)
- foods (57)
- goods (13)
- maintenance (24)
- motion picture (80)
- motorcycle (56)
- music (93)
- paintings (39)
- RUGBY (79)
- tools (43)
- works (10)
- コンピューター (14)
- スポーツ (3)
- テレビ (1)
- 宗教 (3)
- 建築 (62)
- 旅行 (1)
- 時事問題 (12)
- 椅子 (17)
- 科学 (2)
- 言葉 (24)
ウェブページ
りんく
レイモンド・ローウィのカーデザイン2
ケーススタディハウスやアイクラー・ホームズ、イームズやミッドセンチュリーモダン、と言った問題が語り尽くされているとも思えませんし、全てを見知った訳でも無いのですが、こうした文脈に沿った記事や催しは安易な物が多くて、更にフィフティーズのファッションなどと言えば通俗の極みへと墮ちて行きかねません。見飽きた写真とありふれたコメントが並ぶものには行く気も起きないなんて思っていました。カリフォルニア・デザイン1930〜1965展へ行く気になったのはAkiさんのブログにStudebaker Avantiが出ていると書いてあった所為です。
(見た事も、聞いた事も無い物が沢山ありました。特に陶磁器や女性の服装、テキスタイルに対する視点は今までに無い物で興味深く感じました。展示されたアメリカの女性服の立体的な事に感心する一方でその腰回りの巨大な事に尻込みしました。今まで日本の女性が扁平で貧弱に見える事がありました。けれど、日本女性ならではの美しさとも感じる様になりました。陶磁器も図面も全てが大きくて、逆に言えば日本人は小さな物が好きな事を再確認しました。)
で、Avantiです。 Akiさんはペラペラでラジオのデザインの様だと仰ってました。これはローウィデザインを売らんが為のデザインであって商業主義の走狗と捉えた事に依る物でしょう。役に立つ丈夫な道具を目指したジャーマンプロダクツ、ご自身が手元に置いて来たビートル、ポルシェ、ベンツが比較の対象にあったのでしょう。アバンティの相対的な位置を測るのに良い指標だと思います。
一方で、羽振りの良かったアメリカの象徴、ロケット型のバンパーや羽根が一番巨大化したのは59年頃でしょうか。こうしたクルマをデトロイトの売らんが為のデザインとすれば、その後に生まれたアバンティのデザインは随分、慎ましくシンプルで上品だとも言えないでしょうか。
2013-04-14 カテゴリー: automobile, DESIGN | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
レイモンド ローウィのカーデザイン1
SCG38号の中、高島鎮雄氏によると、ピニンファリナのLancia Aurelia PF200には,'51StudeBaker(ローウィデザイン)の影響が見られるとの指摘が五十嵐平達氏によってなされているそうです。左の写真の内、上が’51スチュードベイカー、下がPF200です。如何でしょうか。
ラジエターグリルと左右のフェンダー、三つに分かれていた自動車のフロントマスクを一体化したフルワイズボディの例としてまず上がるのは同じくピニンファリナのデザインしたチシタリアですが、全体のフォルムには感心しても顔のデザインにはこなしきれていない物が有る様に思います。
フルワイズボディの顔を魅力的にする試行錯誤の中でローウィの提案にも意味があったと言う所でしょうか。
2013-04-14 カテゴリー: automobile, DESIGN | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
Daytona Cobra Coupe 1965
二次大戦後、欧州製のスポーツカーに触れてその楽しさに惹かれるアメリカ人が増えました。中には安くて大馬力のアメリカ製V8エンジンを移植すればもっと速くなると考える人もいました。
英国製のスポーツカーACにフォードのV8エンジンを載せたのがキャロル・シェルビーでした。彼は自分の作ったACコブラを売るだけでなく、欧州のレースにも出場しました。
これは行けるとの手応えと同時に、ル・マンなどの長いストレートでは古くて空気抵抗の多いオープンカーの不利に気が付いて、新しくて空気抵抗の少ないクローズドボディが必要だと考えました。ピート・ブロックのデザインしたクローズドボディを載せたのがデイトナコブラです。デイトナのレースでデビューしたのでこう呼ばれたそうです。
1964年からプロトタイプレース(ワールド・マニファクチャラーズ・チャンピオンシップ)に出場して1965年にはタイトルを獲得しました。
これを見ていたのがエンジンを供給していたフォードです。自分の所の上手く行かないフォードGT40をキャロル・シェルビーに任せる事にしました。キャロル・シェルビーは新しいフォードGT40で手一杯ですから、自らのデイトナコブラプロジェクトは中止です。デイトナコブラを売りに出しますが売れません。
1シーズン・2シーズンを戦ったレースカーは消耗仕切ってしまいます。次のシーズンを戦うのにはお金が掛かります。外は新しいボディをかぶっていますが、中身は古いフロントエンジンのスポーツカーです。レースの世界では既にミッドシップのエンジンが当たり前になりつつありました。古いデイトナコブラにお金を掛ける価値があったかという事でしょう。
二束三文になったデイトナコブラの一台が1966年の日本グランプリにやって来ました。クルマは安くなっても、日本にまで運んで、更にレースに出られる様にするのには、当時で1000万程掛かったそうです。その後も長く日本に留まって沢山のレースに出ました。日本のレースファンには馴染みがあります。けれど一線を退いた型遅れがどさ回りで日本にもやって来たと言う感じがありました。十分な手当を受けていた様にも見えませんでした。
その後、日本にあった一台はキャロル・シェルビーの元に戻って手入れを受けた後、ドイツで暮らしているそうです。
最新型しか価値を持たないレースの世界ですが、古くなったレースカーを個人で楽しむ人が増えました。6台しか作られなかったデイトナコブラは最も高い値段が付く様になりました。日本円で5億とも10億とも言われます。暫くぶりに登場する次のオークションでは10〜15億の値段が付くだろうと言われています。
2012-12-31 カテゴリー: automobile, paintings | 個別ページ | コメント (0)
GEMINI
2012-12-08 カテゴリー: automobile, motion picture | 個別ページ | コメント (2)
知ってました?
私は知りませんでした。 伸びたり縮んだりしても割れない六角形は何で出来ているのでしょう。六角形の隙間に石を噛んだりしても大丈夫かな。
2012-10-18 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
オレンジのマクラーレン
小学生だった頃には、勉強なんてしたくない、義務教育が終わったら、ピニンファリナかマクラーレンに丁稚に行きたいと思っていました。 それまでの葉巻型のフォーミュラにウェッジシェープを持ち込んだのはロータスでした。でも、ナショナルカラーだったボディを宣伝に売ったのが小学生には許せません。腹を立てていました。ダウンフォースを生むウェッジシェープを取り込むのに、最初に成功したのはM6.M8のマクラーレンだと勝手に思いました。鋼管スペースフレームからアルミモノコックのバスタブにレーシングカーのフレームが変わって行く中、バルサの両面にアルミを貼る事で軽くて剛性の高いフレームを作るなんて話も格好良いと思いました。(ハニカムサンドイッチなどと同じ話だと思います、)赤いフェラーリに負けない程、オレンジのマクラーレンは良く整理されたCIだったとも思います。 ブルース・マクラーレンが死んで、オレンジ色でも無くなったマクラーレンには関心も無くなりました。丁稚に行ける訳でも無い事も判る様になりました。 幾ら成績が良くてもロン・デニスのマクラーレンは他人事でしかありませんでした。けれどオレンジ色に塗ったMP4-12Cを見た途端に、ブルース・マクラーレンが死ぬ直前、M6.M8をもとにロードバージョンを作りかけていたのを思い出しました
(バルサって今の人は解るかなぁ。サッカーチームの名前じゃありません。軽くて柔らかい木です。桐とか軽くて固いスポンジと言ったら近いかな。模型の材料に良く使われました。模型屋さんってのも最近じゃ見かけないものなぁ。ツーリングカーレースでは市販車のモノコックフレーム、二枚合わせのモナカの中に発泡するウレタンなど注入して強度を上げるそうです。鳥の骨も表面の密度は高くても内部は発泡状態だと聞きました。軽くて強度を稼ぐのには一番の方法なのでしょう。)
2012-08-16 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
自動車のイラストレイション
お知らせするのが最終日じゃ見に行ってもらう訳にも行来ません。間抜けな事でした。
市ヶ谷の山脇ギャラリーでオートモビル・アート連盟の作品展をやっていました。
力のある大きなバイクは、コーナーでスピードを落としても、コーナーの出口でアクセルをひねれば すぐにスピードを取り戻せます。力の無い小排気量のレーサーは、コーナーで如何にスピードを落とさないかが勝負です。大きなクラスよりコーナースピードが速くて、遥かにスリリングです。そうした緊張感が伝わる絵だと思います。
この絵には随分感心しましたが、一方で他の絵には、自動車にまつわる事ってどうして子供じみているのかなとも思いました。皆さん呆れる程にお上手で、その絵の精緻なことにケチの付けようもありません。けれど他の絵画を見る時とはまるで違う部分が喚起される気がします。(ここに取り上げた3点は子供染みた何かを感じない、どちらかと言えば上品な物を選びました)
お芸術に触れた時の高尚な気持ちだけが尊い訳でもありません。お芸術の他にも好きな事があって一向に悪くないとも思います。
懐かしい名前も見つけました。チンチン電車はサンフランシスコでしょうか、細川武志と書いてあります。随分と書き込んだ絵ですが、絵のうまい下手はむしろ簡単な絵で判る事もあります。小学生の頃買っていたAUTOSPORT誌に毎月簡単なイラストが載っていました。細川武志さんって言うんだ、上手いなぁと、いつも感心していました。もう40何年か前の事なんですね。
2012-06-26 カテゴリー: automobile, motorcycle, paintings | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
SL
車両価格16万で買ったクルマで十分満足をしている人間ですから、ベンツには元からご縁もありません。良く出来ているなぁとか、正しいなぁと感心する事はあっても欲しいと思った事もありません。ベンツにお金を掛けるぐらいだったら他にお金の使い道が山程あります。でもパゴタルーフに縦目のSL。これだけは別です、明日目が覚めたら億万長者になっていないでしょうか。メンテナンスに十分なお金を掛けて、ピカピカにして乗りたいなぁ。
近所の空き地に停まっているのを見つけました。ヘッドライトのガラスが一体型で、パゴタルーフにクロムメッキのモールが付いていなければ最高なんだけど。
古いクルマは塗装やゴムの劣化から逃れる事が困難です。下からの湿気も心配です。クルマを買う事でお金を使い果たしてしまって、きちんとした駐車場も用意出来ない、野ざらしで停めておくのは如何な物でしょうか。自分でメンテナンスも出来ない少年たちが古いバイクを買うのも同じ様に心配です。手に入れてからもお金が掛かります。大丈夫かなぁ。
2012-01-30 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
Never let me go
本が話題になったのは随分前だし、映画になった時も社会の中での大きな話題にはなりませんでした。作者へのインタビューをテレビでやったり、私の周りで小さな話題になった時にも映画を見ていません。
やっと映画を見に行けました。作者カズオ・イシグロに対する期待より、’An Education’で見た女優さんに対する興味の方が大きな動機だったと思います。
SF映画の様な特撮も立派なセットも、観光地の様な風景も出て来ません。作中で子供達が壊れたおもちゃやガラクタに大喜びするのを見て、いかにもイギリスだと思いました。古い家を壊すと小さなレンガを一つづつ売り物にする国です。本当に貧しくて質素です。けれど奴隷貿易や植民地経営を何百年もやる中で何にお金を掛けるべきかを知っています。どんなにしみったれても尊厳を守るのにはどうしたら良いか、非人道的な事を粛々と進める為に何が必要かも知っています。勿論、この映画は実際に有った話では有りませんが、質素で教育に手間を掛けるイギリスでこそ成り立つフィクションだと思います。
主人公たちは何故反乱も起こさずそれを受け入れるのか、悪辣な事をやり遂げる為にこそ、質の良い教育と倫理が必要です。
知らない国に行って現地の人たちにマスターと呼ばせるのに何が必要か、二次大戦ではそうした訓練も積まず出て行って、いきなり威張り散らして顰蹙を買った日本人、物質的経済的優位を中国や韓国に取られてアイデンティテイの危機に陥った日本には又とないお手本になる国だと思いました。
全く同じ心と体を持ちながら、一つの社会の中で別の運命を持って暮らす主人公たち、一見同じに見えて違う社会に暮らす彼ら。写真のシーンでは、互いの社会をのぞき合う不思議さ滑稽さが見事に視覚化されています。映画ならではに思えました。本の中ではどんな扱いになっているのか興味が残ります。
感心する事の多い、本当に良く出来た映画だからこそ、幾つか気になる所もあります。主人公達がすがる’猶予’と’ギャラリー’の仕組みは単なる噂だった訳ですが、あまり説得力がありません。主人公がポルノ雑誌を見る理由も切実な物に思えませんでした。
とっても感心したのに幾つか残る疑問、『日の名残り』を見た後も同じ気持ちになった事を思い出しました。
冒頭の、学校にマダムのやって来るシーンではアイボリーのアミがとても奇麗です。今、私は車に格好の良い事を求めませんが、もし今、何に乗るのが格好が良いかと問われれば、ピカピカのアミを乗り回していたらどんなに格好が良いかと思います。大人になった彼らが乗るのはFFになったファミリアです。日本でもヒットした車で友人に載せてもらった事が有ります。
『日の名残り』ではディムラーだったと思います。今は英国王室御用達と言えばロールス、最近はジャガーも有るみたいですが、本来英国王室御用達と言えばディムラーです。二次大戦前にメルセデスを入れるまで、日本の皇室は英国びいきでディムラーも有ったはずです。ジャガーは成り上がりで由緒正しいとは言いかねます。アストンやベントレーは本当の高級車ですが、スポーツイメージが強すぎます。貴族が安物に乗る訳にも行かない、見栄を張る必要は無いけれどシルクハットにはショーファードリブンのリムジンが必要とか、ロールスはちょっとという時にディムラー。時代によってブランドの意味する物も変わりますから、一概には言えませんが、なんだか存在理由が分かった様な気がしました。貧乏人の勘違いかも知れません。
ディムラーは創業の当時、ボートエンジン用にダイムラーエンジンを扱いました。車に関して関係はありませんが、名前の由来は皆様ご存知のドイツ製品によります。日本ではディムラーとダイムラーと言い分けていますが、イギリス人とドイツ人がどう発音しているのか興味が残ります。ジャガーに対する悪口と取られても拙いので申し添えますが、ジャガーは本来バイクのサイドカーのメーカーです。その後安い割に格好だけは素晴らしいスポーツカーを出して、自動車メーカーとしての地位を作りました。アメリカでポルシェを買えない人たちに、ずっと安くて格好の良いフェアレディZが売れたのと同じ理由です。ルマンで戦前のベントレーに匹敵する成績を上げたり、マークツーやS、XKシリーズやC、D、E、typeで評価を確立したのは戦後です。
キーラ・ナイトレイはまったく魅力的ではありません。女優として役そのものを全うしている、素晴らしい出来だとも言えます。このままでは可哀想なくらいです。『ベッカムに恋して』の彼女はとっても魅力的です。
2011-07-16 カテゴリー: automobile, motion picture | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
RENAULT 4
以前に2CVのシートについてエントリーをした時にも、2CVのイベントについて紹介して下さったのがumagurumaさんです。雑誌の記事で見る度憧れていた、グッドウッドも見に行っちゃう羨ましい方ですが、同じ様に一度見てみたいと思っていたレトロモビルについて紹介して下さっています。今年のお題はrenault4だそうです。
YOUTUBEの動画は幾つかの点で大変に興味深いと感じました。一つは2CVに良く似たシートです。人が座るシーンで構造の見当が付く様な気がします。
もう一つはカトルのサスペンションです。最近は径の大きなホイールに巾が広いタイヤを履いて、ほとんどロールもしない程足を固める事が恰好が良いと思われている様です。これは極端に整備された道をとてつもないスピードで曲がろうという時始めて必要な物です。普通の道を普通のスピードで効率の良い移動する為には、成る可く軽いタイヤとある程度のストロークを持った、良く動くサスペンションが必要です。 快適なトランスポーテーションに何が必要か良く判る動画だと思うのですが如何でしょうか。
高速道路で前を行く車を蹴散らしながら追い越し車線をすっ飛んで行く事や、自らに自信の無いステータスを車の値段に語らせるより手の無い人には無縁な車でしょう。最小限の材料とコストで最高の効率、外からどう見えるかより内側がどれだけ快適か、何より乗る事に楽しさを求めた場合、何十年も昔のカトルを超える事はそんなに簡単ではありません。
2011-02-04 カテゴリー: automobile, 椅子 | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT
初めてスピルバーグの’激突’を見た時には、極端に映画の要素を減らしている所為も有って一分の綻びも無い、こんなに完璧な映画を見た事が無い、 凄い監督が出て来たと思いました。その後は、彼に感心をしたことがありません。
やはり彼の作った’1941’はあまりに要素が多くて完全に統制を失った最低の出来です、感心もしません。でも私は好きなんです。映画の好き嫌いは、時として出来の善し悪しと無関係です。
’1941’を遥かに上回る(下回る?)B級映画ですが、私は十分以上に楽しめました。皆さんにも楽しんで頂ける気がします。
日本人なら、’んな訳無いだろう’とあきれる様な映画です。逆に考えれば、アメリカ人が日本に期待する所がこんなに大きいのかとも思えます。アメリカ人の妄想の中で日本はとんでもない国になっています。意外に正確な部分もあって、まるっきりの出鱈目や悪意と言うよりは日本に対する期待或は好意なのでしょうか。ラストサムライを思い出しました。期待或は好意故にとんでもない勘違いになってしまう事があるのかも知れません。
例えれば、映画マッドマックスと実際のオーストラリアの違いって感じでしょうか。この期待に答えるのは難しいなぁ。日本人がこうしたギャップを楽しむのと、知らない人が素直に日本ってすごいなと感心しながら見るのとではどちらが楽しいんだろう。
私達の知っている日本人俳優もちらほら見えますが、大体は端役です。劇中で重要な日本人役はアメリカ在住の韓国人俳優です。カーアクションもアメリカで撮影された様です。
素晴らしい映画だからという訳ではないのですが、機会があったら見て欲しい、’燃えよドラゴン’や’マッドマックス’’カラテキッド’あたりと並べたい所ですが、ちょっと辛いかな。
PS
スピルバーグについて言えば、’1941’が好きだとは言いましたが、本当は’激突’を超える物を作って欲しいと思っています。けれどその後の’インディジョーンズ’は上手くなった’1941’ではあっても、’激突’を超える物では無い気がします。(ルーカスの占める割合も大きいですし)時々シリアスな物も作りますが底が浅くて落胆ばかりしています。シリアスを装ったスピルバーグに比べたら’TOKYO DRIFT’面白いと思うんですけどね。
2010-10-07 カテゴリー: automobile, motion picture | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
AN EDUCATION
映画にはいつも期待しすぎてしまいます。勝手に期待をしすぎて良く落胆もします。逆に全く期待していなかった映画が良いと舞い上がってしまいます。
何が上映中かも知らずに寄ったギンレイホール、4時過ぎに行ったら次の上映は4時20分からです。2本の内1本はまだ見ていないウディアレンでした。これは丁度良い、今日は2本を見て行きましょう。
ウディアレンの1本は、最近見たマッチポイントやバルセロナに比べても特別に良い出来だとは思いませんでした。良く出来てはいるけれど、アニーホールやマンハッタンの様にぐっと来る訳でもありません。名前も忘れてしまいました。
全く知らなかったもう一本 ’17歳の肖像’ 。全く期待していなかったものだから不意打ちを食ってしまいました。女の子の退屈な毎日、そこから見た事も無い大人の世界へと連れて行ってくれる男、そして初めてのセックスとどこかにありそうな話です。林真理子の書いた本もあった気がします。(ストーリー自体は通俗の極みだとケチもつけられます)
男の子が色々な経験をして大人になって行く映画は山の様にあります。大体は初めてのセックスの話でしょう。どれも同じありふれたと言えるものです。けれど傑作がいくつもあった気がします。
どんなにありふれた話も素敵な映画になる可能性があって、どんなに特別な話もつまらない映画になる可能性があります。
訳の分らぬ邦題で損をしている様に思います。原題はAN EDUCATION、この題でこそ映画の意味があると言うものです。まず堅苦しい学校教育があって、それとはまるで違う大人の世界を教育されて、退屈な学校教育を全て否定します。けれど古くさい教養の中の大事なものに気が付いて行く。こういう事なんだと思います。男の私にも十分以上に素敵な女の子映画。全ての女の子と、女の子だった人に是非、お勧めしたいと思います。
PS
あんな間抜けなフランスかぶれは日本だけかと思っていました。
篤姫の人気は日本だけだと思いますが、宮崎あおいは向こうに行っても人気が出るかも知れません。
ロシアのメドベージェフはこの映画の男と似た所がないでしょうか。スタイルカウンシルのミックタルボットも似て見えます。オールバックにしている時には気が付きませんでした。俳優の伊勢谷友介は前髪を下ろすとポールウェラーに似てない事も無い。・・・・役に立たない連想が止まらなくなってしまいました。
ラファエル前派って人気あるんですよね。あれを良い趣味や教養の例にあげるのはどんなものかなんて言ったらイギリス人は怒るかなぁ。イギリス人には一度言ってやりたいと思っていました。絵は良く描けています。でも心根が日本の少女漫画や竹久夢二と同じセンチメントだと。風俗として取り上げるべきものであってファインアートとして取り上げるのは如何なものか。・・・・愛する音楽と絵画の中で自国産はエルガーとターナーとこれぐらいだとすればケチをつけるのも可哀想でしょうか。
ブリストルにナルニア。イギリス人は61年当時の誇りや心の支えを随分失ったのかも知れません。一緒に見たもう一本もロンドンの話でした。ジャガーを自慢していましたが普段乗っているのは日産とトヨタでした。暫くすると韓国製と中国製になるのでしょうか。中国の前で霞んでいく日本人が更に揚げ足を取る様な事は止めておきます。映画の中、61年のイギリスはとっても素敵です。
2010-08-20 カテゴリー: automobile, books, motion picture, music, paintings | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
1/100 P4
小さいときにはマッチボックスのミニカーが欲しかった時もあります。
けれど、見た事も無い外国の商用車ならともかく、身の回りを走っているコロナやブルーバードでは、本物との差が気になって、ミニカーには感情の移入が出来ませんでした。
正確に縮小すれば言い訳ではない、スケールモデルなりの難しさに気が付いたのはかなり大きくなってからでした。
ミニカー趣味には縁が無かったのですが、建築畑では1/100の模型に置ける車は気になります。増してP4と聞いては無視する訳にも行きません。
大好きな車程、実物との違いが気になって、ミニカーが欲しくなる事は無いのですがAkiさんの写真で見る限り予想外に出来が良さそうです。サークルKとサンクスの缶コーヒーのおまけだそうです。今朝近所の3軒程を回ってP4だけを集めて来ました。
1/43いや1/32と言っても信じてしまいそうです。ラジエターのエア抜きやホイールも良く出来ています。
21番のゼッケンもデタラメではありません。67年のルマンで2位に入賞したパークス・スカルフォッティ組の番号です。(キャンペーンの説明にはルマンで優勝と書いてありますがこれは間違い。優勝はフォードマーク4。)
P4ではなだらかなフロントフェンダーには何も付かないか、砲弾型の独立したバックミラーを付けるのが普通です。長いストレートを持つルマンの為だけに空力対策としてバックミラーを覆うカバーが付けられました。おまけP4のフロントフェンダーの後半に段が着いているのが分るでしょうか。
これはルマン以外の写真ですが、9番11番を付けたP4には砲弾型のミラーが着いているのが分ります。
下の白黒の写真がルマンだけで施された空力対策です。21番は伊達じゃありません。特別なルマン対策を忠実に再現してあります。
良い大人が宇宙戦艦ヤマトやガンダムの話をしても許される世の中でしょうか。おばさん達がヨン様に熱をあげても仕様がないで済むものでしょうか。大人の女性が大きなぬいぐるみに埋もれていたら、私はちょっと気持ちが悪いです。この歳になって10才の時と同じ話をするのは威張れた話じゃ無いのは分っています。
子供の時には何十年もすれば少しは賢くなるのだろうと思っていました。けれど3台並んでP4がフィニッシュするデイトナの写真、いまだに脳裏に焼き付いてます。思い出すと10才の時と同じ気持ちになります。
缶コーヒーのおまけよりちょっと立派です。UMAGURUMAさんのグッドウッドのお話も是非御覧になって下さい。
2010-08-01 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
ダイソンその他
久し振りに行ったアクシスで見た物を幾つか。
噂の扇風機を見て来ました。確かに安全で静かで格好が良い。リング内周スリットからの風でリング中央に風を起こす、霧吹きやキャブレタと同じ様な仕組みだと思います。結果としてファン自体の風量より大きな風が送れる。というお話です。本当にお上品で楚々とした風でファン自体より大きな風を起こしている様には思えません。ちょっと微妙な所です。けれど、風の質感がまるで違います、これに比べると今までの扇風機の風が乱暴で洗練されないモノに感じるのも確かです。(展示用に風量を落としていたのかも知れません)
こちらはフレームだけでなく、リムまで木製の自転車。凄い、工芸品ですね。
今日(11/2)NHKのテレビに出て来ました。東京で100年だか200年続く船大工(51歳)が作っているのだそうです。ドイツの自転車展に呼ばれて260万だかで3台売れたそうです。
こちらはアウトウニオン型のペダルカー。220万円とかですって。
2009-10-30 カテゴリー: automobile, bicycle, crafts, DESIGN | 個別ページ | コメント (5) | トラックバック (0)
カングー
膝の具合も良くなって来たので、久し振りにテニスの合宿に行ったらS夫妻がグロリアをカングーに乗り換えていました。
高速を飛ばすのにも、峠を攻めるのにも向かないし、旦那さんが欲しがっていたBMWやレクサスの偉さもありません。でも中が広くてシートが良くて快適です。
新車で買えるのは今が最後だと言う事です。どうせ私は手も足も出ませんが折角の機会なので、内寸を測らせてもらいました。私にとっては、バイクが積めるかどうかが最大の関心事です。
助手席を外せば、長さは2200mmぐらいまで積めそうです。リアゲートの高さは1200mm、サイドミラーやアップハンドルは難しいところです。ハンドルを握ったまま、スロープを押し上げても人間の頭が辛そうです。手放してしまったシングルドカならともかくTX650は難しそうです。実物は想像以上に魅力的でしたが、一番当てにしていたバイクのトランスポーターとしては背がぎりぎりです。 お金も無いので悩む必要は無いんですけどね。
2009-06-08 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
エコカーはエコか?
エコ替えなんていう乱暴な話が大腕を振ってまかり通る事への疑問、資源を消費して新しい車を作る事に比べて古い車を大事にする事が何故いけないのか。一端気になると色々な物が目に入って来ます。こうした私の個人的な状況の他に、世間全体にエコカーと言った美談に対して疑問が噴出して来ている様な気がします。
'プリウスを例にとると、カタログに表記されている35.5km/Lという燃費で
10万Km走行した際に排出したCo2は6.5tになりますが、販売される前に
すでに約6tを排出していると読み取れます。
出展:Goo-net
要するに、誰かが地球によかれとプリウスをオーダーすると、
その度に6tもの巨大なCo2が瞬時に地球へと排出されるのです。
これは、同クラスのガソリン車がエッチラオッチラと年数かけて50000km走行し、
ようやく排出するCo2と同等なのです。
それなら同クラスの車を、年数かけてさらに50000km走らせるのが、
中長期的に見れば環境にも貴方のお財布にも遥かに優しい、エコな行為といえるのです。即ち、環境に優しいとされるクルマにそそくさと乗り換える行為こそが、
反エコな行為であり、国家が行っている減税措置は、環境に貢献どころか
破壊を促進する「消費は美徳」とされた40年前の高度成長期に誕生した、
まさに化石のような愚策以外の何者でもありません!'
以上はアユケンブログからの引用です。コメントには反論も多い様ですが、論拠に多少の不備はあっても一理ある様に思います。
エコチュー更にこちらがそのネタモトだそうです。
とまぁこう言った話が幾つかネット上に散見されるわけです。ただエコに対して噴出する疑問の中にはとんでもないバカ本が多いのも事実です。 (以前から漠然と感じていた期待(胡散臭さと言っても良いのですが)に見事応えてくれる幻冬社が好きです。)武田 邦彦も参照して下さい。
トヨタのコマーシャルとどちらが正しいのか。まだ反論が提起されたにすぎません。
2009-05-11 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
サスティナブルな車

近所で久し振りに、ヴァンデンプラスADO16を見かけました。
かつてキラ星を並べた様に栄華を誇ったイギリス車も、名前と看板だけを残してその実態は雲散霧消してしまいました。
アメリカのビッグ3までが壊滅の危機にあって、小さな車やハイブリッド車を持つ日本車こそが明るい未来を持っている・・・・本当でしょうか。
持続可能な社会。自動車会社が生き残ることをそう呼ぶのであれば、イギリスにはその資格がありません。
小さな島に、片手に余るメーカーのひしめく日本は、世界でも稀な自動車会社持続可能な社会と呼べます。
逆に一台の車が生き延びる事から考えるとどうでしょう。昔は日本でもトヨタ・ホンダはどんなに古い車の部品でも供給してくれました。けれど合理化など言われる様になって古い部品の供給は放棄されてしまいました。日本国内でさえ古い日本車を維持するのは大変です。イギリス車はいまだにほとんど全ての部品が調達可能です。メーカーが無くなっても必ず誰かが部品を作ります。それにお金を払う人と古い車が残っています。
自動車会社と一台の車どちらが生き残れる社会が望ましいのでしょうか。
勿論、生き延びなければならないのは会社や車でなく人間です。
ガソリンは食わないけれど、作るのに大量の資源の必要な新しいプリウスと古い車を大事にするのとではどちらが人間に優しいのでしょうか。
一度誰かにキチンと説明をしてもらわないと’エコ替え’を素直に聞けません。
なんてのは建前であって、綺麗に磨かれたヴァンプラをみて古い車を大事にする事が素敵に思えたというのが本音です。
リアクォーターピラーには塗膜の浮き上がりが見られます。指で押すとぱりんと割れて赤い錆が見えて来るでしょう。素敵に見えるけれど大変なんですよね維持するのは。
2009-05-10 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
ルノーメガーヌ
暫く前に、車検に出した車を取りに行ったら、お店に古いサンクの4ドアが置いてありました。ウェストラインが水平で後ろの窓が広く感じます。絶対的な広さ以上に窓の大きさが室内を広く見せています。最近の車はウェストラインが後ろに行く程跳ね上がっていて、その分後ろの窓が小さい。格好は良いんだけど後部座席に座った時の閉塞感は如何な物か、などと思っていました。
以前に試乗した時に、同じ事をルノーのメガーヌにも感じていました。黒の内装で後部座席では狭さ以上にたこ壷に押し込まれた様な感じがしました。メーターやシフトレバーの縁の取って付けた様な銀色も気になりました。
今度の那須行きではマサさんのメガーヌに乗せてもらいました。マサさんのメガーヌはマイナーチェンジ後の後期型で微妙に顔が違っていました。言われるまで気が付きませんでした。マイナーチェンジがあった事さえ知りませんでした。日本の市場に受け入れられたとは言えないメガーヌの中でも後期型は更に少ない様に思います。ベージュの明るい内装の所為で後部座席でも閉塞感がありません。メーターの縁の銀も気になりません。二日一緒いたら、あの特別なお尻と窓も気にならなくなりました。いやむしろあのお尻こそが素晴らしい、最後には愛着さえ感じました。
オートバイを運ぶのには車内の広さ以外に高さが必要です。スロープから荷台の床まで勢いを付けて押し上げる為に、ハンドルを持ったまま車内まで人が走り込める事が大切です。屋根の無いトラックでは天気に左右される事が多いし、大きなバンでは乗用車の様な小回りや乗り心地は期待出来ません。バイクの為の車内の広さと最小の外寸、乗用車の様な乗り心地。こう言った条件を兼ね備える車はルノーのカングーしかありません。それにルノーの伝統に違わずシートがとても良いのも確かめてあります。今はバイクも壊れたままだし、ガレージもありません。いつかそうした環境が揃ったら一番に欲しいのはカングーです。
今乗っている車は放っておいても壊れないし、ウィングとスカートや金色のホイールが恥ずかしいけれど、乗ってしまえば気にならない。お金も無いし、買い替える気はありません。けれど、フランス車が少し恋しくなりました。
もうひとつ気になるのはトヨタのプロボックスです。あれを艶消しのサンドベージュに塗ったらイラク仕様の軍用車みたいで良いなと出た時から思っています。
以上今気になる3台でした。
2009-04-22 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (16) | トラックバック (0)
2CVの椅子

子供の頃、真っ先に気になったのは最高時速でした。
暫くすると0-400mって何だろう。加速を決めるのはパワーウェイトレシオらしいと気が付きます。初めて車重と馬力が気になり始めました。
エンジンの弁形式や搭載位置、駆動方法、サスペンションの違いが気になりだして、小学校の5年6年になるとやっぱりダブルウィッシュボーンが格好いいなとか、FJの後輪にマクファーソンストラットは格好が悪いなとか思っていました。レースの記事では結果より、フレームの進化やブレーキやショックの構成に関心を奪われました。
(軽自動車のエンジンを使うFJではホンダN360が良く使われました。FFだったN360のエンジンだけでなく駆動系からフロントサスペンションまでをまるごとフォーミュラのミッドシップに転用する事も良くありました。)
生意気な事を言っても,実際には乗った事も無いし、まして負圧式とCRキャブ、SUキャブレターとウェバーがどう違うか解っていた訳でもありません。本当の所は何も知りませんでした。ウェバーの方がどう優れているのかも解らないくせにSUより格好が良いと思い込んでいました。同じ様に外側の格好が気になる事はあっても、内装は子供の私にとって関心の外でした。なにせ乗って中を見る機会などほとんど無いのですから。
大学に入って友人のクルマに乗せてもらったり、社会に出てあちこちで乗せてもらう機会が増えて来ると、昔は気にならなかったインテリアが気になり始めます。
最高時速や0-400mなんて街の中で気になる事はまずありませんが、シートの座り心地や表地の材質は室内で過ごすのに大きな問題です。
ごてごてと模様の付いた国産車はすぐ背中やお尻が痛くなりました。素っ気なくても、良く出来た固いシートの方が長く乗っても楽だと教えてくれたのは、ゴルフだったと思います。
(レカロのシートに乗せてもらったのは大分後でした)
ベンツのシートも固くて素っ気ないものでした。
それに比べて、ひかるさん(勤めていた事務所のお客さん、代官山に沢山レストランを持っていました)のローバーは本物のウッドパネルとコーデュロイのシートが心地よくて素敵でした。オープントップに出来るスポーツカーや、ショーファードリブンの運転席でないかぎり皮よりファブリックのシートの方が具合が良いと思います。古いローバーは外に見栄を張る所が無くて、乗る人の為に質の高い何かがあった気がします。
私は大好きでしたが、もう大分歳をとっていて、七里ケ浜の海岸を雨の中何百メートルも押した事があります。
その後、第三京浜の出口でブレーキが利かなくなって大変だったと聞きました。
同じイギリス、ウッドパネル貼りのジャガーにも何度か乗せてもらいましたが、あまり良いとは思いませんでした。
その後、随分色々なジャガーに乗せてもらいましたが、ローバーに感じた見栄を張らない質の高さと言ったものを感じる事はありませんでした。
勤めていた事務所の親分がホンダシティを買いました。68万とかだったと思います。
その頃、フィアットのパンダは本国で買っても120万ぐらいしたと思います。
本当のコストダウンは平面ガラスを使うことじゃない。安くする為には他にやる事があるのじゃないか。2CVやカトルとは時代が違う。シティを見てみろ。
最初、パンダには批判的でした。
甲州街道沿い、お店の前に並んでいるのを、夜中にのぞいたらドアに鍵が掛かっていません。
中に入って驚きました。外なんかどうでも良い、お金なんて掛けなくていい、内装のセンスだけでこんなに素敵になるんだ。
そのインテリアに夢中になりました。クルマのインテリアに初めて独立した価値を感じました。
大好きなパンダのインテリア、シートのモトネタがこの椅子です。コノリーレザーのシートより、2CVの鉄フレームのハンモックシートに心奪われるのは私だけでしょうか。プルーベの椅子について語る時、一方で此の椅子を知らないのは語るに落ちると思います。
2CVは生誕60年、行事も色々あるみたいです。シトロエンマニアや自動車好きでなくても楽しめると思います。2CVのパリ観光
教えて頂いたのはUMAGURUMA氏のブログhibicoreからです。ドカのシングルとアルファのSZにお乗りです。最初は拙ブログのドカにだかCXのエントリーにコメントを頂いた様に思います。違ったかな。バイクとクルマ以外にも音楽や読書、建築と巾の広い見識をお持ちで、何より海外の事情にも通じていらっしゃる。教えて頂く事が多くて楽しみにしています。
PS
60周年記念モデルの2CVエルメスで、ハンモックシートの仕組みが良く分かります。厚い座布団の中がどうなっているのか分からない(ブラックボックスってのはもう少し難しい物に使う様な気がします)普通の車のシートより、簡単な仕組みが可視化されている所が素敵です。ただ実際には何年かでダメになる輪ゴムの交換が面倒だとの意見もあります。
2008-10-01 カテゴリー: automobile, 椅子 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
Flaminio Bertoni
シトロエンが、変なクルマだという世間の認識は、もう何十年も変っていません。
前輪駆動車を、戦前から大量生産し、その後も変なクルマを作り続けて来ました。
(戦前にも、小さな規模の前輪駆動車生産は、他の例があります。フランス以外で前輪駆動が大量生産されるのは1959年のミニまで待たねばなりません。)
ただ、実際に乗ってみると、全てに理由と理想と信条があって、気まぐれや変態趣味でない事が分かります。(乗る人間が、変態趣味とのそしりをまぬがれるかどうかは微妙です)
むしろ、いつもまわりの顔色ばかりを見渡してクルマを作り、自らの理由と理想と信条の無いクルマを世界一売る事こそがクルマを作る目的だと言われると、何か目的を間違えていないかと言いたくなります。
最近のシトロエンはドイツ車や日本車の真似をするようですけどね。
何十年にも渡って作られた変なクルマは、それぞれが違う目的を持っていて、お互いにまるで違っています。戦前のトラクシオンアボンから、2CV、DS、AMIまでが一人のデザイナーの手になるとは知りませんでした。
これまで、シトロエンについて、個人名は創始者のアンドレ シトロエン以外に聞く機会がありませんでした。
それも、アンドレの後を継いだ経営者ピエール ジュール ブーランジェの自己を吹聴する輩を蔑む性格に依るものだと分かりました。
入院前に買った、’シトロエン 革新への挑戦’には知らない事が沢山載っていました。
見た事の無い写真も多く、見た事のある写真も写りが遥かに綺麗です。
大きくて綺麗な写真と、聞いた事のない人達の素敵な仕事の話。
とても素敵な本でした。お薦めします。
もう一つ、デザイナーの名前が多く知られる事の無かった理由は、イタリア人 フラミニオ ベルトーニ という名前がイタリアのベルトーネと紛らわしかった所為もあるのかもしれません。
2008-09-02 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
クルマが先かヒコーキが先か
出先で2時間程、時間が出来てしまいました。
冷房の効いた喫茶店で時間を潰すのに、久し振りにNAVIを買いました。
もう長い事連載している、’クルマが先かヒコーキが先か’のページが楽しみです。先月はメッサーシュミットだったみたいです。戦闘機と三輪車の話でしょう。今月はハインケルの話です。飛行機と戦後のキャビンスクーターの話です。He111爆撃機の絵で嬉しくなってしまいました。
子供の頃作ってもらった、べらぼうに出来の良いプラモデルを思い出しました。
映画バトル オブ ブリテン(邦題は空軍大戦略)では、大陸側の飛行場
滑走路の遥か先にまで並んでいたのが忘れられません。
メッサーシュミットBf109を上回る性能を持ちながら、政治的な理由で採用されなかったHe100Dも昔から憧れていました。ほとんどの二次大戦独軍機については色や迷彩について詳細な資料がプラモデル塗装の為に揃っています。ただコンペに破れて正式採用のなかったハインケルの戦闘機については白黒写真しか見た事がないので何色だったのか分かりません。
児玉英雄のレンダリングと同じく連載が本になっています。
1冊目は持っています。その後もまとめて読みたくなりました。
その後、別の本を探すのにたまたま入った本屋で、ふと見上げたら目の前に2冊目と3冊目が並んでいました。
こんな事もあるんですね。
2008-08-05 カテゴリー: automobile, books | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
秋葉原のトヨタ
秋葉原の事件については、あまりに色々な人が色々な話をしていて、私自身で何かを考えるという事もしていませんでした。
MADCONECTIONへのakiさんの書き込みを読みました。
解雇されると思い込んだのは犯人自身の誤解だと思っていました。
けれど派遣が全て解雇される予定が実際に存在していた事。
彼の勤めていた工場がトヨタそのものであった事。
この二つの事実を私は知りませんでした。
名も知らない工場で、勝手に勘違いをした犯人が狂気に走ったのと、
日本を代表する企業に一方的に解雇されたのでは、
少し、印象が違って来る様に思います。
情報操作とまで言っていいかどうか、単にトヨタはラッキーだったのでしょうか。
もうひとつ。
居酒屋タクシー自体がそんなに大きな問題とは思えません。
毎晩、電車が無くなるまで働いてるひとは多いと思います。
そのうち何割が何万も掛けてタクシーで帰れるのでしょうか。
何万もの交通費が税金で支払われている事が問題だと思います。
増して、飲んで帰るタクシー代が公費で賄われたり、お姉ちゃんを送るのに使われるのは論外です。
こっちも論点がそらされている気がします。
2008-06-14 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
fiatの電気自動車
 fiatのお膝元、トリノ市全体で使うシェアリングカーだそうです。
fiatのお膝元、トリノ市全体で使うシェアリングカーだそうです。
燃料電池と太陽電池による電気自動車です。
スイスの山の中ならともかく、内燃機関による自動車産業の城下町でも電気ですか。
緑のタイヤも実用化されるのかどうか心配ですが、なかなか格好がいいと思います。
此の手の小さい車は、本来フィアットやプジョー、ルノーの得意とする所だったはずです。
先代の500や、パンダ、サンク、205に309どれもが魅力的でした。
でも現行車のどれもがあまり素敵に思えません。
テレビのCMに出て来る三菱の電気自動車はなかなか良いと思っていました。カラーリングも素敵です。
三菱がエンジン付きの軽を電気にするなら、フィアットも500なんか止めて、これの内燃機関版を作ればいいのにと思いました。
白と黄緑がエコって言うのは日本の家電屋さんの戦略による物かとも思いました。
結果的に誰もが乗れる潮流になったってことなのでしょうか。
白と黄緑のタイヤを塗り替えてしまえば、目新しい所がある訳じゃない、スマートあたりと見分けがつかないなんて悪口も言えそうです。
新しい所が無くても、私はなかなか良いと思いますけどね。
2008-06-04 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
Xantia
 それまで乗っていたルノー5 tsは、パワーが有る訳でも無いし、固いサスペンションや太いタイヤもない。速く走れる訳じゃない、世の中で言うスポーティーとは違う車だった。
それまで乗っていたルノー5 tsは、パワーが有る訳でも無いし、固いサスペンションや太いタイヤもない。速く走れる訳じゃない、世の中で言うスポーティーとは違う車だった。
けれど、良く廻る小さなOHVと、ストロークの深いサス、クロースしたミッションとでシフトを繰り返し、アクセルで前後の荷重を考えるのが本当に楽しい、運転する事がスポーティーな車だった。
それまでバイクに乗るのが楽しくて、車なんかに乗ったらバカになると思っていた。こんなに運転の楽しい車があるとも思わなかった。
車体やエンジンに一切の故障は無かったけれど、オルタネータと言った補機類、パワーウィンドウやクーラー、ファンがいつも壊れて最後には持ち切れなくなった。
次の車は年取った親を乗せるのに、4ドアで大人4人がゆっくり乗れて、クーラーが効いて故障しない車を捜した。最初は国産を捜したけれど、故障しない国産車は中古でもあまり値段が落ちない。
300万を超える車が5年か6年で1/6以下になったりするのはシトロエンぐらいだった。
同じ輸入車でもベンツやBMWやアルファと言った人気車にこんな事はあり得ない。
良く壊れる変な車といった評判は一度付いたら中々取れないのだろう。
お店の人が、今のXantiaはそんなに壊れないよと言うのを信じることにした。
クーラーのガスが漏れて、二度程足した。天井の内張がはがれて垂れて来た。6年乗って、壊れたのはそれだけだった。
前のサンクのように運転が楽しいことも無いし、これ見よがしの高級感も無いけれど、いつでも安心して乗れる上質な車だった。他の車に乗る度に自分のXantia に乗りたいと内心思っていた。
ここへ来て、FサスのストラットからLHMが漏れだした。ブレーキホースからタイミングベルト、消耗部品も替える所が色々出て来た。 リアフェンダーも私がぶつけたままだ。屋根の塗装も禿げて来た。去年の夏、大人5人で茨城に出かけた時にはクーラーも少し頼りなかった。
全部直そうとすると結構なお金が掛かる。車検も近づいて来た。お金があれば手を入れて乗り続けたいけれど、94年型だから13年目。残念だけれど、もっと安く済む次の車を捜す事にした。
2007-03-11 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
トヨタ
暫く前に熊本県警がトヨタのリコールについて問題にした時も、あらゆるメディアが積極的には取り上げなかった。
三菱の時にはあれほど騒いだのが嘘のようだ。
要するに宣伝費の違いなのだそうだ。ほとんどのメディアがトヨタの広告費を気にして追求出来ないらしい。
今度はやはりトヨタの系列で労災隠しと不当解雇だそうだ、又うやむやにされるのだろうか、忘れないように書いておこう。
http://www.asahi.com/national/update/0918/TKY200609180211.html
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06080326.cfm
2006-09-20 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
トヨタテクノミュージアム産業技術記念館
トヨタが愛知万博の手前あたりに車のミュージアムを作っているのは知っていた。自分の所の2000GTやTOYOTA-7はともかく、デューセンバーグからルーズベルトのパッカード、ベントレイ4.1/2、ロールスではシルバーゴースト、ドライエと相当な力の入れようらしい。
一度見たいとは思っていたけれど、こちらは知らなかった。名古屋市内、旧豊田紡績工場跡のトヨタテクノミュージアム産業技術記念館。
レンガ積みの壁に木造トラスのノコギリ屋根、昔の工場そのまま、広大なミュージアムにしてある。(名古屋駅からも大して離れていない。)
入り口脇のスペースに歯車やカム、発電、いろいろなメカニズムを子供にも遊びながら学べる部屋がある。その展示にお金の掛っていることに驚く、あのケチンボトヨタがと、びっくり。
けれどこれは、御通しにも刺身のつまにもならない、その後の繊維機械館の膨大な事と言ったら、上野の博物館も科学博物館も貧弱すぎて比べられない。有史以来の紡績から、全てを実物で説き起こす。産業革命以来の機械の発展も全ては紡績機械と自動織機の実物で再現するぐらいの意気込みだ。その質と量、まじめさは他に例を見ない。もう少しアトラクティブでもとは思うけれど、それもトヨタの体質だろう。
あまりの量と内容の濃さに精も根もつきはてて、順路を進むと自動車館はもっとでかい。ここまででまだ前菜かと思った途端、腰が抜けそうな気がした。巨大なプレスでボディパネルを打ち出すところから、それを全自動でロボットが溶接するところまで、他にもとても書き切れないほどの機械が工場そのままに動いている。興味のある展示も山のようにあるのだけれどとても見きれない。
外国の車のノックダウンで始めたのとは訳が違う。車以前に機械工業に対する膨大な蓄積があったからこそ、今日のトヨタがある。多分そういう事が言いたいのだろう。
恐れ入りました。
トヨタ恐るべし。
2005-12-07 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
ポルシェ
フォーミュラ-1はドライバーのチャンピオンシップだけれど、もうひとつメーカーの為にマニファクチャラーズチャンピオンシップというレースがあった。
それはプロトタイプ(本来は原形とか試作車という意味だけれど、レースの世界では市販車とは別の、屋根付きでタイヤの覆われたレーサーをさす。)という車で争われていた。
60年代、ヨーロッパ中心だったレースに、巨大な資本と7リッターV8のバカ力を武器にフォードが進出した。醜いフォードマーク2と4リッターV12の素晴らしく美しいフェラーリP4が争っている頃、巨大な恐竜たちの足元を這い回る小さな哺乳類のように、隙あらば小さなクラスから入賞を狙っていたのがポルシェだった。
日本でも、プリンスや日産、トヨタといった巨大なメーカーに小さなプライベーターが一矢を報いんとして挑戦する時、選ばれるのは必ずポルシェだった。
レースでも小さなクラスから、次第に総合優勝を争うクラスになって、917がマニファクチャラーズもCAN-AMも常勝を誇るようになった頃、ポルシェに対する気持ちに変化が起きた。
市販車の世界でも、あくまでも極く少数の好きな人の買う車であって、有名人が金持ちになると買う車ではなかった。
車がひと各々の嗜好で選ばれたり、工学的な判断の対象である内はいいけれど、ある数を超えると、そうした範囲を超えて社会的な意味を帯びて来る。
ポルシェやベンツを買ったと言えばそれだけで単なる車の問題では済まない意味をしょって立つことになる。いくらおれのは356だといっても、分かってくれる人は少ないだろう。
小学生の頃、’フェルディナンドポルシェの伝記’や’フォルクスワーゲン世界を制す’を読んだり、輸入車ショウでミツワのパンフレットをもらったりのポルシェびいきだった私もポルシェにはほとんど興味をなくしてしまった。
ポルシェに何を期待するかは人によって違うのだろう。
成るべく簡単な空冷水平対抗を、リアかミッドシップに載せたスポーツカー。極端に言えばビートルの皮を剥いで新しい皮を被せただけで、こんなに楽しいスポーツカーが出来る。なんて所を期待する。(こんな期待は誰もしないか?)
356には、フェラーリや最近のポルシェのように技術の限りを尽くした最高の贅沢ではなく、スーパービートル、フォルクスワーゲンに毛の生えたスポーツカーであって欲しいと思うのは侮辱だろうか。
現在のポルシェ乗りの9割は侮辱だと思うのだろう。最高のスポーツカーを作ることこそがポルシェの素晴らしい目的ではあるのだけれど・・・
そういう意味では914が私にとって一番ポルシェらしいポルシェだったのかも知れない。
2005-09-08 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (3) | トラックバック (1)
ルノー メガーヌ
ここしばらくのルノーのアバンギャルドぶりには驚いていた。メガーヌについても格好が良いとは思わなかった。むしろ何枚かの写真を見る度に、不整合で不器用な様にあきれた。なぜこうまで攻撃的なのかとも思った。日産のティーダに顔が似てるな、何か関係があるのかなとも思った。
けれど街中で実物を見ると、マッスの動的な事には感動した。ワゴンを選ぶ事で特徴的なリアウィンドウから逃げる手もあるけれど、折角ならあの毒まで込みでのメガーヌだとまで思うようになった。新車なんて買えるはずもないけれど、試乗に行って来た。現行車種に興味が湧いたのは久し振りだ。
顔もティーダとは随分違っていた。速さもクラスも違い過ぎて比べるのは失礼かも知れないが、昔のサンクを思い出した。アクセルを踏んでも、シフトをしても、ひとつひとつの操作が楽しいところが似ている。今のシトロエンXantiaも見えやハッタリを期待しなければ上質で安心出来る良い車だけれど、こういった楽しさは無い。
あの前衛的な内装や狭い後席には必ずしも賛成しかねるけれど、見に行った去年からずっと気になっている。
ラグーナとカングーのシートにも感心した。ルノーは本当にシートが良い。
古いルノーのめんどうを見ているお店に言わせると、ルノージャポンになってから、部品がきちんと出て来ないと言っていた。
ルノージャポンは丁度日産がリストラを進めていた頃だ。丁度良い受け皿だったのかもしれない。
一方日産の人からはルノーの部品番号のでたらめさに困っているとも聞いた。
昔は何年型の何と言えば、でたらめな番号からちゃんと引っ張り出してくる人がいたのだろう。
ルノーメガーヌ
2005-06-14 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (1) | トラックバック (0)
MUSEUMS BY YOSHIO TANIGUCHI
暫く前にジャンヌーベルの建築展をみた。彼の建築自体は興味があるし、見せてもらえる情報の質も量も素晴らしいのだけれど、せっかくの内容のサービスの仕方に消化の悪いものが残った。
その点で、奇をてらう事のないストレートな展示が建築そのものと同じように素晴らしい。
新しいメディアについて行けない年寄りの負け惜しみかもしれない。
MOMAの建物も綺麗だけれど、赤いチシタリアと黒いヴィンセントを見てコレクションが羨ましくなった。私だったらウェッジシェープが蔓延する直前の赤くて丸いスポーツカーを集めて一部屋作りたい。デトマソヴァレルンガ、フェラーリP4、アバルトシムカ1300 OT、ジウジアーロのアルファロメオカングーロが欲しいなぁ〜。
谷口吉生のミュージアム展はオペラシティで6/26まで。
2005-04-25 カテゴリー: automobile, 建築 | 個別ページ | コメント (0)
HIDEO KODAMA gallery
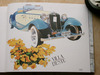 子供の時からやみくもに自動車の絵を描いてきて、子供のいたずら書きとは違うプロの絵をまとめて見ることができたのは、中学の時に穂積和夫の自動車のイラストレーションという本を買った時が初めだった。それ以来、今では自分で描くこともないけれど、人様の描く自動車の絵が常に気になっていた。中学生にとって、ジウジアーロのレンダリングはラファエロより大事だったのに、この年になって見るとルネッサンスの絵画と比べられる様な自動車の絵などはひとつも無かった。そこまで行かなくても、商業用のイラストレーションもカーデザインのレンダリングも含めて上手な人はたまにいても。下品にならない人となると本当に少ない。そんな中で永年ドライバー誌の表紙を描いていた松本秀実氏は下品になることがない、そしてべらぼうに上手い。そしてカーデザインのレンダリングに関して言えばオペルの児玉氏だろう。NAVI誌に毎月載るレンダリングを毎回楽しみにして来た。一冊の本になったのを早速買い入れた。
子供の時からやみくもに自動車の絵を描いてきて、子供のいたずら書きとは違うプロの絵をまとめて見ることができたのは、中学の時に穂積和夫の自動車のイラストレーションという本を買った時が初めだった。それ以来、今では自分で描くこともないけれど、人様の描く自動車の絵が常に気になっていた。中学生にとって、ジウジアーロのレンダリングはラファエロより大事だったのに、この年になって見るとルネッサンスの絵画と比べられる様な自動車の絵などはひとつも無かった。そこまで行かなくても、商業用のイラストレーションもカーデザインのレンダリングも含めて上手な人はたまにいても。下品にならない人となると本当に少ない。そんな中で永年ドライバー誌の表紙を描いていた松本秀実氏は下品になることがない、そしてべらぼうに上手い。そしてカーデザインのレンダリングに関して言えばオペルの児玉氏だろう。NAVI誌に毎月載るレンダリングを毎回楽しみにして来た。一冊の本になったのを早速買い入れた。
松本秀実
HIDEO KODAMA gallery
2005-03-15 カテゴリー: automobile, books | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
C1
 ルノーは日産と、プジョーシトロエングループはトヨタと組むのだそうだ。ベンツのAが中身はコルトで、シトロエンの新しいC1はトヨタのヴィッツなのだそうだ。ハイドロでなければシトロエンではないなどとは思っていない。AXはAXでとても楽しい車だったし、サクソも106とは微妙に違うし。それはそれで楽しみだと思っていた。出たばかりのヴィッツは中々カッコ良い、特にサイドウィンドウはとても良い。中身はトヨタでも足廻りの味付けをやり直してもらえればいいなと思っていた。けれど、これはあんまりカッコよくないな。ヴィッツの方がかっこ良くて値段も半分だったりするのだろうか。そういえばベンツのAってコルトとどのくらい値段が違うのかな。中身は日本製の高いデジカメもライカって書いてあると欲しくなったりしちゃうのだろうか。
ルノーは日産と、プジョーシトロエングループはトヨタと組むのだそうだ。ベンツのAが中身はコルトで、シトロエンの新しいC1はトヨタのヴィッツなのだそうだ。ハイドロでなければシトロエンではないなどとは思っていない。AXはAXでとても楽しい車だったし、サクソも106とは微妙に違うし。それはそれで楽しみだと思っていた。出たばかりのヴィッツは中々カッコ良い、特にサイドウィンドウはとても良い。中身はトヨタでも足廻りの味付けをやり直してもらえればいいなと思っていた。けれど、これはあんまりカッコよくないな。ヴィッツの方がかっこ良くて値段も半分だったりするのだろうか。そういえばベンツのAってコルトとどのくらい値段が違うのかな。中身は日本製の高いデジカメもライカって書いてあると欲しくなったりしちゃうのだろうか。
PS その後C1と同じプラットフォームのトヨタ車はアイゴーという名前だという話をあちこちで聞くようになった。このアイゴーとヴィッツの関係はまだ不明。どこかで調べなくちゃ。
2005-03-11 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
C6
 CXのページにトラックバックして頂いたお陰でジュネーブショーの新しいC6を見る事ができた。ウィンドウグラフィックにCXやGSを思わせる所があるなと思ったのだが、リアウィンドウがえぐれているのに気が付いた。これはどうやらたまたまという訳ではなく、あきらかにCXを引用してのことらしい。アルファの156の成功あたりから、ブランドイメージの継承として歴史的なディテールの引用に皆さん熱心だ。同じシャーシをいくつかのブランドで使いまわそうとするなかで、違う顔にしようとすれば仕方がないののかもしれない。アルファに関して言えば成功しているし、好感も持っていた。ただシトロエンにはlookbackよりはlookforwerd(この場合、前を見るという意味にはならないのでしょうか?期待するでも勿論構いませんが。)で行って欲しかった。
CXのページにトラックバックして頂いたお陰でジュネーブショーの新しいC6を見る事ができた。ウィンドウグラフィックにCXやGSを思わせる所があるなと思ったのだが、リアウィンドウがえぐれているのに気が付いた。これはどうやらたまたまという訳ではなく、あきらかにCXを引用してのことらしい。アルファの156の成功あたりから、ブランドイメージの継承として歴史的なディテールの引用に皆さん熱心だ。同じシャーシをいくつかのブランドで使いまわそうとするなかで、違う顔にしようとすれば仕方がないののかもしれない。アルファに関して言えば成功しているし、好感も持っていた。ただシトロエンにはlookbackよりはlookforwerd(この場合、前を見るという意味にはならないのでしょうか?期待するでも勿論構いませんが。)で行って欲しかった。
2005-03-11 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
CX

 最初に、エアコンやオートマがなきゃイヤダと言い出したのは、多分アメリカ人だろう。その後の便利だけれど無くても良いようなおまけなら日本人の大得意だ。どちらも暫く前の欧州車には付いていない事が多かった。各々の国やメーカーで随分と違う車を作っていたのだと思う。ハンドルには風船を、バンパーには対衝撃性を、色々な基準が増える度に世界中の車が似て来る。操作の方法も共通化が進んでいる。一切のコクピットドリル無しに乗っても運転に困る事が減った。良いことかもしれない。
初めてCXのドライバーズシートに座ると途方に暮れる。メーターから、ウィンカーのスイッチまで、全てが今まで乗って来た車と違う。
なんとか走り出すとハンドルの感覚も不思議だ。私は慣れるまで随分時間が掛った。
ただ慣れてくると、全てに理由のある事が分かってくる。今の世の中は30年前にフランス人の考えた未来とは違ってしまったのが残念だけれど、30年前に考えられる限りの理想や未来を実現している所が凄い。エアバッグだなんて言い出す前だったのだろう、一本ハンドルのお陰でメーターの視認性は抜群だ。ハンドル一本も構造的には相当な無理をしている。リムと軸を2本、3本で繋げばずっと簡単なのに。
自分達の考える理想や未来のためには手間も惜しまない。そのくせとても未来的だった外観とは裏腹にエンジンそのものは古い直4のOHVのままでまるで蒸気機関車のようだ。
どうも日本では誰が考えても一つの答えになることや、お金の掛らない事を、合理的と言ってしまいがちだけれど、人各々が持つ各々の理屈を大事にする事が合理だとすれば、意味がまるで逆になる。
全てが思想的根拠と未来に対する希望で出来た車に一旦慣れてしまうと、隣の車と同じにしておけば良い、それぞれが考えることを放棄した全ての車が情けなく思えて来る。
私のXantia(20年後のフランス人の合理性はずっと日本人よりだ)と何ヶ月か交換させてもらったお陰で貴重な経験が出来た。友人H氏に感謝したい。
車の名誉のため付け加えれば普通の人は10分程、早い人は二.三度、角を曲がると慣れるそうだ。
ハンドルを切ると大きくロールした後、長い魚が身震いする様にコーナーを脱出していくのは、慣れると病みつきになる程の快感だ。
PS今乗れば古く感じる直4 OHVのエンジンも70年代の発売時期には特別古い訳でもなかったのだと思う。30年前の車だと言う事を忘れがちだ。当時どれだけ’未来’だったのだろう。
もっとも50年代に発表されたDSの方が遥かに未来的だったと言う話もある。現行シトロエンに未来を感じられないのが残念だ。
最初に、エアコンやオートマがなきゃイヤダと言い出したのは、多分アメリカ人だろう。その後の便利だけれど無くても良いようなおまけなら日本人の大得意だ。どちらも暫く前の欧州車には付いていない事が多かった。各々の国やメーカーで随分と違う車を作っていたのだと思う。ハンドルには風船を、バンパーには対衝撃性を、色々な基準が増える度に世界中の車が似て来る。操作の方法も共通化が進んでいる。一切のコクピットドリル無しに乗っても運転に困る事が減った。良いことかもしれない。
初めてCXのドライバーズシートに座ると途方に暮れる。メーターから、ウィンカーのスイッチまで、全てが今まで乗って来た車と違う。
なんとか走り出すとハンドルの感覚も不思議だ。私は慣れるまで随分時間が掛った。
ただ慣れてくると、全てに理由のある事が分かってくる。今の世の中は30年前にフランス人の考えた未来とは違ってしまったのが残念だけれど、30年前に考えられる限りの理想や未来を実現している所が凄い。エアバッグだなんて言い出す前だったのだろう、一本ハンドルのお陰でメーターの視認性は抜群だ。ハンドル一本も構造的には相当な無理をしている。リムと軸を2本、3本で繋げばずっと簡単なのに。
自分達の考える理想や未来のためには手間も惜しまない。そのくせとても未来的だった外観とは裏腹にエンジンそのものは古い直4のOHVのままでまるで蒸気機関車のようだ。
どうも日本では誰が考えても一つの答えになることや、お金の掛らない事を、合理的と言ってしまいがちだけれど、人各々が持つ各々の理屈を大事にする事が合理だとすれば、意味がまるで逆になる。
全てが思想的根拠と未来に対する希望で出来た車に一旦慣れてしまうと、隣の車と同じにしておけば良い、それぞれが考えることを放棄した全ての車が情けなく思えて来る。
私のXantia(20年後のフランス人の合理性はずっと日本人よりだ)と何ヶ月か交換させてもらったお陰で貴重な経験が出来た。友人H氏に感謝したい。
車の名誉のため付け加えれば普通の人は10分程、早い人は二.三度、角を曲がると慣れるそうだ。
ハンドルを切ると大きくロールした後、長い魚が身震いする様にコーナーを脱出していくのは、慣れると病みつきになる程の快感だ。
PS今乗れば古く感じる直4 OHVのエンジンも70年代の発売時期には特別古い訳でもなかったのだと思う。30年前の車だと言う事を忘れがちだ。当時どれだけ’未来’だったのだろう。
もっとも50年代に発表されたDSの方が遥かに未来的だったと言う話もある。現行シトロエンに未来を感じられないのが残念だ。
2005-02-22 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (1)
Sphere

(普通、前輪がマクファーソンストラットであれば、ボンネットをあけると左右のタイアハウスの上、ストラットの頂部に緑の球がついている訳です。)
鉄の球の中に横隔膜のようなゴムの膜がついています。ゴム膜の上半分には高圧の窒素ガスが入っていて空気バネになっています。石に乗り上げると縮められたシリンダーから鉄球の下半分にLHMが流入して空気バネを縮めます。(流入する穴の大きさを変えることでダンピングの調節が出来ます)コイル等の鉄バネでは入力に対して直線的な反応をしますが、本当は縮み始めは柔らかく奥に行くほど堅くなる、二次曲線状の反応が理想的です。もちろん現在のコイルサスペンションでは、バネ定数の違う二種類のコイルを組み合わせるなどの対策をしていますが、基本的に空気バネの方が優れています。
ただ、現在の技術では完全な気密或いは真空を維持するのは難しく高圧のガスもゴムの膜等を通して少しづつ漏れていきます。そういったわけで、2万キロか3万キロに一度、一個8〜9千円の鉄の球を取り替えれば最高の乗り心地が維持出来ます。
(インターネットで輸入すると送料別で3500円程度、サービスマニュアルでは4万キロに一度だったかな?)
これをディーラーにまかすと前後で5万ほど掛かります。インターネットで英国の部品屋さんを見ていると、向こうでは、新車と保険は高い様ですが、出来る程度の事を自分ですれば、自動車を維持するのは、日本でディーラーまかせにするより、大分安いのだということも分かって来ました。
2004-10-22 カテゴリー: automobile, maintenance | 個別ページ | コメント (2)
LHM

車体の姿勢の変化に応じてそれぞれのシリンダーに送り込むオイルの量を変えることで車体の姿勢と乗り心地を積極的に制御出来る。
普通の車は道路の凸凹に対してそれぞれのバネが勝手な反応を繰り返してるに過ぎない、左右は鉄の棒で繋げても前後はまったく無関係に動いている。
大きなうねりを乗り越える時、荷物を沢山載せた時、ブレーキを踏んだ時、アクセルを踏んだ時、姿勢変化の無いこと、乗り心地の変わらないことは普通のサスペンションには望むべくもない。
今は普通のサスペンションも格段の進化をしているけれど、乗り心地を重視してバネをやわらかくすると高速で頼りにならず、高速のためにバネを堅くすると乗り心地が悪い、そういったサスペンションに比べれば、開発当時は、手間暇をかけるだけの意味があったのだろう。
(サイバーショットの宣伝で山高帽のおじさんが乗っているDSのデビューは1955年)
実を言えば、進化した国産車の柔らかいバネの乗り心地に、町中では敵わない所もある。細かいごつごつを結構拾う。ただ高速に乗ると雲の上を滑るような感覚と、ビシッとした操作感が両立するところは独特だ。
又、普通のダンパーは何万キロも付けっぱなしだけれど、オートバイのフロントフォークオイルは1年か2年で必ず替える。そのたびに汚れてヘドロのようになったオイルが出てくる。何万キロもそのままで良いものだろうか。ダンパーごと4輪付け替えるとかなりの出費になる。
その点ハイドロニューマティックシステムならぼ、液を交換してバケツを掃除すればいい。
そうしてシトロエンの乗り心地や姿勢、足回り全てを制御している体液がこのLHMだ。(ブレーキフルードにもなっている)
奇麗な緑色が使っていると段々濁ってくる、丁度青焼きの現像液に似ている。フィルターの汚れ方もそっくりだ。
ディーラーでの指定純正はTOTAL製で1L1700円だか1800円だけれど、こちらはペントシンで1L850円。
モダンサプライ
2004-10-19 カテゴリー: automobile, maintenance | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
BX
 どう言う訳かある時期、身の回りに同一車種が増えることがある。ヒット車種がある時代を思い出すきっかけになる事も多い。大学の1年2年のころにはあちこちで初代アコードに良く乗せてもらった。ウェストラインが低くメーター廻りもシンプルでそれまでの日本車のデラックス指向とは明らかに違う価値観を感じた。小さめのメーターボックスはBMWの02シリーズを思わせた。坂本先生のアコードも学内で良くみかけた。大学の後半には初代のゴルフが多かった。バブルのころのシーマ現象とは無縁だったけれど、シトロエンのBXにはあちこちで乗せてもらった。
どう言う訳かある時期、身の回りに同一車種が増えることがある。ヒット車種がある時代を思い出すきっかけになる事も多い。大学の1年2年のころにはあちこちで初代アコードに良く乗せてもらった。ウェストラインが低くメーター廻りもシンプルでそれまでの日本車のデラックス指向とは明らかに違う価値観を感じた。小さめのメーターボックスはBMWの02シリーズを思わせた。坂本先生のアコードも学内で良くみかけた。大学の後半には初代のゴルフが多かった。バブルのころのシーマ現象とは無縁だったけれど、シトロエンのBXにはあちこちで乗せてもらった。
黒木さんのお手伝いをしている時に乗せてもらった初代BXはボビンメーターと紫に近い青がとても綺麗だった。初めて運転させてもらったのは、バイク屋さんの赤いBXだった、銚子の方の温泉に行った時だと思う、乗り心地は黒木さんの車で知っていた。ずっと前に乗せてもらったGSに比べて遥かに普通の車に近付いたように感じていたのだが、長い距離を乗ると国産車との違いが良く分かった。ブレーキのストロークが短いのにも驚いた。
中学の頃のカーグラフィックの表紙の裏がシトロエン、裏表紙がミツワのポルシェで’シトロエンはアバンギャルド’といった宣伝をしていた。(トラクシオンアボン(FF)とリアエンジンリアドライブ(RR)を前衛と後衛に引っ掛けていたのだと思う)。ごく少ない変人の乗り物だったのが、BXで一挙に数が増えて西武自動車はともかく慣れないマツダでは面倒を見切れなかったのだろう。日本中でよく壊れる変な車という評価を不動のものにしてしまった。
そのわりに黒木さん以外に私の友人も2台つづけてBXに乗っていた。気に入っている人も多かったのだと思う。あれだけ多かったBXもそういった訳で近ごろでは見ることも減ってしまった。
今でも自分で手を入れて乗っている友人がいて、BXに乗せてもらう度に、早くは無いけれど十分なエンジン、大人4人がゆっくり乗れる限りに小さい車体、座った時の窓の高さ、硝子なりにえぐれたドアの内側、そして乗り心地(LHMやスフィアに手をいれてあれば)とても良い車だと思う。もう何年もたつ車だからそれなりに手入れが必要だけれど、オーナーが自分で出来る範囲が多い。
もちろん、たまには途方に暮れる時もあって、この時も難しくてハイトコレクター(車高調整装置)の修理で何度か泣きそうになった。
自動車いじりの師匠にお出まし願って、苦労をしてやっと直った時はお手伝いの私も本当に嬉しかった。
2004-10-03 カテゴリー: automobile | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)










